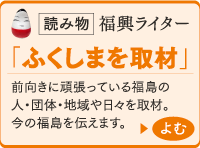ふくしまの女性たちの物語 三原由起子さん
短歌朗読2011年3月11日以降のわたし(2)
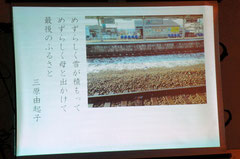
食堂に鍋焼きうどんの煮えるまで母と語りて窓は眩しき
お土産に「なみえ焼そば」携えて車窓より見る手を振る母を
めずらしく雪が積もってめずらしく母と出かけて最後のふるさと
最後の帰省になってしまった、震災前の実家での情景を詠んだ3首。浪江町に大室屋という食堂がある。両親が自転車店とおもちゃ店を営んでいたため、家族がそろう食事の思い出はほとんどない。たまたま母と大室屋でなべやきうどんを食べた。そのおいしさが忘れられない。 浪江町に、雪が降るのはめずらしい。めずらしい出来事が起きた日に撮った駅のホーム。キオスクにいるおばちゃん。駅前にある「なみえ焼そば」の製麺所。高校時代、いわきまで3年間通った由起子さんにとって、駅にはたくさんの思い出がつまっている。思い出は震災と原発事故によって壊された。失ったから気づく、なにげない日常の大切さ。
「十年後も生きる」と誓いし同窓会その二ヶ月後にふるさとは無し
由起子さんが卒業した学校では、女性の厄年の幹事は男性が、男性の厄年の幹事は女性がやるのが恒例だ。集まるとすでに何人かが故人になっている。震災の年の1月に、中学時代の同窓会が開かれた。「十年後も生きようね」と誰かが言った。その2カ月後、震災が起きた。
阿武隈の山並み、青田が灰色に霞む妄想
爆発ののち 由起子さんの好きだった青田の光景。まだその情景を見る機会がないが、セイタカアワダチソウが生い茂り、元の美田が想像できない状況になっているだろう。 百年の商いつないでいく矢先見えない敵は空から降りぬ ひいお婆ちゃんの代からはじまり、父母が継いだ商店は約百年続いた。やがて子供たちへと引き継がれていくはずだった。しかしあの日、空から降ってきた「放射能」という敵によってつぶされてしまう。由起子さんは言う。「まさか、こんな中途半端な状況におかれるとは、夢にも思わなかった。原発が爆発したら日本中が終わると思っていたのだから」と。
ふるさとを遠く離れて父母と闇を歩みぬ
螢を追って 山形県に避難している両親と共に、小野川温泉に行き螢を見たときに詠んだ歌。この歌を「茂吉の歌に通じるようだ」と言った人がいた。歌人斎藤茂吉は、山形県生まれである。山形県で生まれた歌。「詠む場所が、言葉を生むのだろうか」短歌には技巧よりもむしろ、身体からわき出てくる言葉が大切なのではないか。ことに震災後は、身体からわき出てくる言葉を大切にしている由起子さんである。(3へ続く)