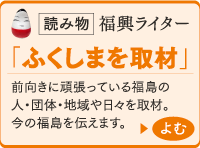ふくしまの女性たちの物語 三原由起子さん
短歌朗読-2011年3月11日後のわたし(3)

ふるさとを遠く離れて父母と闇を歩みぬ
螢を追って 山形県に避難している両親と共に、小野川温泉に行き螢を見たときに詠んだ歌。この歌を「茂吉の歌に通じるようだ」と言った人がいた。歌人斎藤茂吉は、山形県生まれである。山形県で生まれた歌。「詠む場所が、言葉を生むのだろうか」短歌には技巧よりもむしろ、身体からわき出てくる言葉が大切なのではないか。ことに震災後は、身体からわき出てくる言葉を大切にしている由起子さんである。 「正月をふるさとで過ごす帰省客」になれないわれらは前を向くのみ 家族、あるいは同級生と会うひととき。ふるさとを離れ東京で暮らす身にとって、心躍る帰省シーズン。それを3.11の震災と原発事故が、砕いてしまった。被災者の悲しみを知ってか知らずか、報道される帰省のニュース。それがふるさとを失った身には辛い。辛いけど、決して下は向かない。ただ前を向くのみ。
空がただ明るい真昼 真夜中が永遠に続くようなふるさと
浪江町にあったショッピングセンター近くの、震災後の風景。日中なのにもかかわらず、人影のない不気味な風景。「この風景をどう思う?」由起子さんは再び会場の父に問う。父は答える。「まさにある大臣が言ったように『死の町』だ」。「死の町」と評した大臣はすぐに辞任に追い込まれた。本当のことを伝えたくない人たちによって。 むき出しの原子炉建屋に作業する人らがありて続く日本 浪江町に原発はない。しかし東京電力の社員、下請け業者、さらにその下請けと原発で働く町民は多い。同級生が集まれば、原発をめぐる話も出てくる。そういう状況が、電力を供給されている側の人たちには伝わりにくい。今も原子炉で働く人たちの手によって支えられているということを、私たちは想像しなければならない。
二年経て浪江の街を散歩するGoogleストリートビューを駆使して
行政、支援団体、企業の協働によって、浪江町の様子がGoogleによって見られるようになった。カメラは細い路地にまで入り込んでいる。感謝しつつも、未だ生活することができないふるさとを、インターネットを通して見る寂しさ。この気持ちは、ふるさとを失った人でないとわからないだろう。

沈黙は日ごとに解けていくように
一人ひとりと声を束ねて
原子力発電所で働く人の多い浪江町。そのせいか「脱原発」とは言いにくい雰囲気もある。震災後、原発を巡って同郷の友人たちと意見の食い違いがあった。 震災から2年経ち、あのときのこと、「脱原発」を言い続けることに疲れたと時々思う。でも考える。ここでくじけてはいけないと。 震災を通してつながった人たちがいる。震災がなければ、つながることのなかった人との縁を大切にしたい。だから由起子さんは伝え続けたいと思う。
短歌を詠むことを通して
震災後、ふるさと福島県に帰って来た若者たちがいる。「ふるさとの復興のために」という気持ちと共に、県外にいると、福島県の状況がわかりにくいという声も聞く。また「県外で生活していると、ふるさとの大変さを忘れてしまいそうでこわい」という感想も。それを思うとき、東京で生活しながらふるさとのことを想い、発信し続ける由起子さんのパワーのすごさ。これからもみなさんにご紹介していきたい。